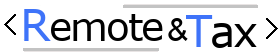お手軽でお得な法人設立サポートをご用意しています。
はじめまして。
フルリモート対応の税理士 川畑英之と申します。
こちらのウェブサイトにご訪問いただきありがとうございます。
これから法人を設立されるお客様のサポートもフルリモートで承ります。
法人を設立するとなると面倒な手続きが多そうだし、結構お金がかかりそうなイメージがありませんか?
しかし、実際はそれほど大変なことではありません。
法人は簡単に設立できますのでご安心ください。
また、当方が提供している法人設立サポートで会社を設立していただくと次の特典を受けることができます。
・法人設立した際に必要な届出一式(法人設立届出や青色申告承認申請書など)の提出を無料サービスで承ります。
・提携している司法書士のご厚意により、相場に比べて数万円ほど安い金額で、法人を設立することができています。
ここでは、当方で提供している法人設立サポートで設立登記をする場合の手続きと費用についてご紹介します。
必要な手続き
法人設立パックにおいて必要な手続きは次のとおりです。
・会社名、本店住所などの必要事項をシートに記入する
・個人の印鑑証明を取得する
・判子3本セットを作成する
・資本金を振込む
以上です。
基本的にはこれだけで済んでしまいます。
上記の各項目の具体的な内容はここでは割愛します。
実際に会社設立を検討する段階になったときに詳しくご案内しています。
とにかく、法人設立の手続きは意外と簡単なのだということをご理解いただければと思います。
必要な費用
法人を設立するためには、登録免許税や司法書士報酬などの登記費用がかかります。
合同会社であれば13万円前後、株式会社であれば28万円前後が相場だといえます。
当方の法人設立サポートをご利用の場合は、提携している司法書士のご厚意により、相場に比べて数万円ほど安い金額で、法人を設立することができています。
また、顧問契約をお申込みいただいた場合には、法人設立した際に必要な届出一式(法人設立届出や青色申告承認申請書など)の提出を無料サービスで承ります。
株式会社か合同会社か
法人格を合同会社と株式会社のどちらにすべきかというご質問をよく受けます。
この2つの法人格について比較すると、それぞれ次のような特徴があります。
合同会社
・設立コストが安い
・社会的認知度が低い(≒社会的信用度が低い)
・出資者は原則として役員として扱われる
株式会社
・設立コストが、合同会社より高い
・社会的信用度が高い
・株主(≒出資者)でも役員になる必要はない
上記の違いを比べただけではどちらが適切かを一概に判断することは難しいところです。
基本的には合同会社でも問題ないと思います。
法人設立で留意しなければならないことでご説明していますが、副業禁止の会社にお勤めの方は、念のために株式会社にしておくとよいかもしれません。
合同会社をお選びになった場合でも、株式会社に変更することは可能です。
ただしそのときは別途追加のコストがかかります。
いずれは株式会社にしたいという構想があるのでしたら、追加のコストのことを考えて最初から株式会社を選択するのも1つの手だといえます。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ年商2,000万円超の事業者様は法人化すべき?タイミングと税務メリットを徹底解説
年商2,000万円以上の事業規模に成長した場合、法人化(会社設立)を検討するタイミングに差し掛かっている可能性があります。個人事業主として事業を継続する場合、高額な所得税や消費税の負担が発生し、結果として事業の利益を圧迫することがあります。一方で、法人化することで法人税の適用、節税対策、社会的信用の向上などのメリットを享受でき、事業のさらなる拡大が見込めます。
本記事では、法人化を検討すべき適切なタイミングやメリット、法人化に伴う税務上の変化や節税のポイント、さらに法人化によるデメリットや注意点について詳しく解説します。また、会社設立時に税理士がどのようにサポートできるか、さらにフルリモート対応の税理士と長期的にパートナーシップを築く重要性についても触れます。
法人化を考えている事業者様にとって有益な情報を提供しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 売上規模に応じた法人化のタイミングと主なメリット
法人化の適切なタイミングを見極めるには、以下の2つの基準が参考になります。
① 年商1,000万円を超えた時点
個人事業主として年間売上(年商)が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します(消費税の「基準期間」による規定)。これにより、売上の10%程度の消費税を納める必要が生じ、手元に残る資金が減少します。
法人化を行うことで、設立後2期(最大約2年間)は消費税の免除が適用され、資金繰りの負担を軽減できます(※適用要件あり)。これは法人を設立する大きなメリットの一つです。
② 所得(利益)が600万~800万円を超えた時点
個人事業主として事業が軌道に乗り、年間の所得(利益)が600万~800万円を超えると、所得税・住民税の負担が急増します。累進課税制度により、課税所得が増えると適用される税率も高くなり、所得税率は20~23%超、住民税を含めると30%以上になることもあります。
法人化を行うと、所得を「法人」と「個人」に分散できるため、税負担を抑えることが可能です。法人税の軽減税率を活用すると、利益800万円までの法人税率は15%と、個人の所得税率より低く抑えられます。また、役員報酬の設定により所得税の最適化が可能になり、節税の幅が広がります。
法人化の目安と今後の方針
以上のように、「年商1,000万円超」または「利益600~800万円超」のいずれかの基準を満たす場合、法人化を検討するタイミングといえます。
もし年商2,000万円以上の規模で事業を運営されている場合、すでに法人化のメリットを最大限活用できる状況にあると考えられます。特に、フルリモート対応の税理士がサポートすることで、法人化後の経理や税務管理をスムーズに進められます。
法人化についてお悩みの事業者様は、ぜひフルリモート対応の税理士にご相談ください。オンラインでの対応が可能なため、どの地域からでも専門的なアドバイスを受けられます。
- 大幅な節税効果
法人化すると、個人事業主の事業所得を「法人所得」と「役員報酬(給与所得)」に分けることで、税負担を分散できます。個人事業主の場合、すべての利益に累進課税の所得税・住民税が課されるため、所得が増えるほど税負担が大きくなります。しかし、法人にすれば利益の一部を役員報酬(給与)として支払い、法人の経費として計上できます。
また、個人として役員報酬を受け取る際には、給与所得控除が適用されます。例えば、
- 年収500万円の場合:約150万円が控除対象
- 年収800万円の場合:約200万円が控除対象
このように法人と個人に所得を分散させることで、トータルの税金を抑えることが可能です。浮いた資金を広告費・仕入資金・人材投資に回すことで、さらなる事業成長につなげられます。 - 消費税の納税が当面免除される
法人を新設した場合、原則として設立1期目と2期目は消費税の納税義務が免除されます(※適用要件あり)。個人事業主が年商1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生しますが、そのタイミングで法人化すれば、最長2年間は消費税を納めずに済むため、消費税相当額(売上の10%)をまるごと事業の運転資金に充てられます。
ただし、この免税を受けるには「資本金1,000万円未満」で法人を設立する必要があります。また、2期目も免税とするためには、1期目前半6ヶ月の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下であることが条件となるため、計画的な法人化が重要です。フルリモート対応の税理士に相談すれば、最適なタイミングを見極めた法人化のサポートを受けることができます。
- 社会的信用力の向上
法人化すると、取引先や金融機関からの信用度が向上し、事業運営上のさまざまな場面で有利になります。例えば、- 金融機関からの融資が受けやすくなる
- 掛け仕入れ(信用取引)の枠が拡大される
- 法人登記により事業の透明性が高まる
個人事業主は開業届一枚で始められるため、金融機関や取引先からは信用度が低く見られがちです。しかし、法人の場合、設立手続きが必要なため「事業継続の意思が強い」と判断されることが多く、取引の幅が広がります。さらに、法人登記により所在地や役員情報が公的に登録されるため、事業の実態が第三者から確認可能になり、信用度が向上します。
- 事業承継・拡大の柔軟性
法人化すると、将来的な事業承継や事業拡大の選択肢が広がります。例えば、- 株式や持分の譲渡による事業売却が可能
- 新たな出資を受けて資本金を増強できる
- 法人として従業員を雇いやすくなる
個人事業の場合、事業を譲渡する際に「事業譲渡契約」を結ぶ必要があり、手続きが煩雑です。一方、法人なら「株式譲渡」によってスムーズに経営権を引き継げます。また、法人なら新たな投資を受けやすく、事業の拡大に向けた資金調達もしやすくなります。年商2,000万円を超える事業者様にとって、さらなる成長を目指すための重要なステップとなるでしょう。
2. 法人化で変わる税制:法人税・消費税のポイントと節税効果
法人化すると、個人事業主と法人では適用される税制が大きく異なります。特に影響を受けるのが、法人税と所得税の違い、消費税の扱い、そして法人化後に活用できる給与所得控除を使った節税対策です。
法人化を検討する際、事業の利益や経費の取り扱いがどのように変わるのかを正しく理解し、最適な節税方法を選択することが重要です。本章では、法人化後の税制の変化とそのメリットを詳しく解説します。
法人化をスムーズに進めるためには、フルリモート対応の税理士がサポートできるため、全国どこからでも専門的なアドバイスを受けることが可能です。法人化に伴う税務の変更点をしっかりと把握し、最適なタイミングで法人化を進めましょう。
法人税と所得税の違い:税率構造と控除の比較
法人化すると、課税対象が「法人の所得」となり、個人事業主とは適用される税率や控除の仕組みが大きく異なります。特に、税率構造や経費の扱いにおいて、法人化のメリットを活用することで税負担の最適化が可能になります。
1. 税率構造の違い
個人事業主の場合、1月~12月の事業利益がそのまま個人の所得と見なされ、累進課税(5%~45%)の所得税と一律10%の住民税が適用されます。利益が増えるほど税率が高くなり、最大55%(所得税45% + 住民税10%)に達する可能性があります。
一方、法人税の税率は個人の累進課税と比べて幅が狭く、一定の水準に抑えられるため、所得が増えるほど法人の方が税率面で有利になります。具体的には、中小法人(資本金1億円以下)には以下の税率が適用されます。
| 課税所得 | 法人税率(軽減税率適用) |
|---|---|
| 800万円以下 | 15% |
| 800万円超 | 23.2% |
さらに、法人には法人住民税・法人事業税などの地方税が加わりますが、個人所得税の累進税率と比較すると、一定以上の利益がある場合は法人の方が税負担を抑えられる傾向にあります。
2. 控除・経費の違い
法人化すると、経費として計上できる項目が広がるため、課税所得を圧縮する手段が増えます。個人事業主では、基礎控除や青色申告特別控除(最大65万円)などが適用されるものの、経費として認められる範囲には制限があります。
一方、法人では以下のような支出が損金(経費)として算入可能となり、節税効果が期待できます。
- 役員報酬(自分への給与)
→ 役員報酬として適正額を支払うことで、法人の利益を圧縮できる。 - 役員退職金の積立
→ 退職金規定を作成することで、退職時に大きな控除を受けられる。 - 法人契約の生命保険料
→ 一部の生命保険料は法人の経費として計上可能。 - 交際費
→ 中小法人は年間800万円まで全額損金算入可能(個人事業主は厳しく制限される)。
このように、法人化により課税所得を圧縮できる仕組みが充実しており、節税の自由度が高まるのが大きなメリットです。
3. 決算期の自由な設定
法人は決算期を自由に設定できるため、事業の繁忙期や在庫調整に合わせた利益計上の調整が可能です。個人事業主は1月~12月の暦年で課税されるため、売上が集中した場合、調整が難しくなります。
例えば、決算月を売上が落ち着く時期に設定することで、利益の変動を抑え、税負担を最適化する戦略がとれます。事業の特性に合わせて決算期を選択できる点も法人化の大きなメリットです。
消費税の扱い:新設法人の2年間免税と注意点
法人化を検討する際に重要なポイントの一つが消費税の免税措置です。個人事業主の場合、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納付が義務付けられます。
例えば、年商2,000万円規模の事業者様であれば、すでに毎年消費税を納めているケースが多いでしょう。しかし、法人化を行うことで、設立後最長2年間は消費税の納税を免除できる可能性があります。
新設法人の消費税免税制度
新しく法人を設立した場合、消費税の免税制度を活用できるケースがあります。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 設立1期目(初年度)
資本金を1,000万円未満で会社を設立すれば、設立初年度(事業開始から最初の会計期間)は自動的に消費税の免税事業者となります。これは、基準期間(消費税の課税・免税判定の基準となる前々期)が存在しないためです。
ただし、資本金を1,000万円以上にすると設立当初から消費税の課税事業者となるため、免税を適用したい場合は、資本金を1,000万円未満に抑えるのが一般的です。 - 設立2期目(2年目)
原則として2期目も消費税は免税となります。ただし、「特定期間」(設立1期目の開始日から6ヶ月間)の売上や給与の支払総額が一定の基準を超えると、2期目から課税事業者になってしまう点に注意が必要です。
具体的には、以下のいずれかの条件に該当すると、2期目から消費税の納税義務が発生します。 - 設立1期目の前半6ヶ月間の課税売上高が1,000万円超
- 設立1期目の前半6ヶ月間の給与支払額合計が1,000万円超 したがって、1期目の前半は売上を1,000万円以下に抑える、あるいは役員報酬の支払い時期を後半にずらすなどの工夫をすれば、2期目の免税を維持できる可能性があります。
免税期間のメリットとインボイス制度の影響
消費税の免税期間を最大限活用すれば、設立後2期分(最大4年間)の消費税の納税義務を回避できるため、事業資金の余裕が生まれます。本来、納税に充てるはずのお金を、仕入資金や設備投資、新規事業の開拓に回せるのが大きなメリットです。
一方で、2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書保存方式)により、BtoB取引を行う場合、免税事業者であることが不利に働くことがあります。具体的には、取引先がインボイスを発行できない免税事業者との取引を避ける可能性があるためです。
ただし、取引相手が一般消費者中心である場合(例:ネット販売や小売業など)、免税のメリットの方が大きいケースが多いでしょう。
逆に、法人相手の取引が多く、インボイス発行が求められる場合は、2期目から課税事業者を選択することで取引の円滑化を図るという選択肢もあります。
給与所得控除を活用した節税の仕組み
法人化後の節税対策の一つとして重要なのが、給与所得控除の活用です。これは、「役員報酬を経費として法人の利益を圧縮する」という節税策と密接に関係しています。
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、給与を受け取る人(会社員や役員)に認められるみなし経費であり、年収に応じて一定額が控除される制度です。個人事業主の事業所得には適用されませんが、法人を設立し、自身を役員として給与を受け取ることで、この控除を利用できます。
例えば、年収500万円の場合は約150万円、年収800万円なら約200万円が給与所得控除として適用され、課税所得がその分圧縮されます。これは、実際の支出を伴わない「自動的に適用される経費」ともいえるため、法人化による節税メリットの一つとなります。
法人化した場合の節税効果(具体例)
具体的な節税効果を、法人化の有無で比較してみましょう。
法人化しない場合(個人事業主のまま)
事業所得が800万円の場合、青色申告特別控除を適用しても課税所得は約800万円となります。
所得税(23%)+住民税(10%)の合計税率は約33%となり、税負担は大きくなります。
法人化して役員報酬を800万円とする場合
- 会社側:役員報酬800万円を経費計上できるため、法人税の負担はほぼゼロ。
- 役員(個人)側:給与所得控除(約204万円)を適用した後の課税所得は約596万円。
- この結果、個人の所得税率も約20%台前半となり、住民税を含めた実効税率も30%以下に抑えられます。
- さらに、給与所得控除の204万円に対する税負担(約60万円相当)が発生しないため、その分の節税が可能です。
このように、法人化することで給与所得控除を活用し、個人の税負担を軽減しながら、法人の利益を圧縮することが可能です。
さらに節税効果を高める方法
法人化による節税策は、給与所得控除だけではありません。
- 所得分散による節税
- 配偶者や家族を役員・従業員として雇い、給与を支払うことで世帯全体の税負担を軽減。
- 個人事業主の「専従者給与制度」よりも法人の方が柔軟に設定できる。
- 法人向け税額控除の活用
- 所得拡大促進税制など、法人向けの税制優遇措置を活用することで、さらに節税の余地がある。
このように、法人化すると給与所得控除を最大限に活用できるだけでなく、その他の税制優遇も利用できるため、法人と個人トータルでの税負担を最小限に抑えることが可能です。
3. 法人化のデメリットと注意点:社会保険負担や経費管理の変化
法人化には多くのメリットがありますが、デメリットや注意点も存在します。法人化を検討する際は、メリットだけでなく、これらの点も十分に理解し、総合的に判断することが重要です。
ここでは、法人化に伴う社会保険の負担増、経理・事務作業の増加、会社形態の違い(株式会社と合同会社の比較)について解説します。
1. 社会保険の加入義務とコスト負担
法人化すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が発生します。これは、法人の代表取締役や従業員が法律上、厚生年金保険・健康保険に加入しなければならないルールがあるためです。
たとえ代表取締役1人の会社(役員のみ)であっても、会社設立と同時に社会保険の適用事業所となるため、社会保険加入は必須となります。
社会保険の負担額の目安
- 保険料は労使折半(会社と個人が半分ずつ負担)
- 標準報酬月額に応じて給与の約30%前後が保険料として徴収
- 会社負担分:約15%、個人負担分:約15%(給与から天引き)
例えば、役員報酬を月50万円支給する場合、
会社が負担する社会保険料は毎月約7万5千円、
個人(役員)が負担する社会保険料も毎月約7万5千円となります。
個人事業主のまま国民年金・国民健康保険に加入していた時と比べ、社会保険料の負担が大幅に増加するため、法人化後の資金計画には注意が必要です。
2. 社会保険加入のメリットとデメリット
法人化による社会保険の負担増はデメリットとなりますが、一方で保障内容が充実するというメリットもあります。
社会保険のメリット
- 将来の年金額が増える(国民年金より厚生年金の方が給付水準が高い)
- 傷病手当金(病気やケガで働けない期間に給付金が支給される)
- 出産手当金(産前産後休業中の生活保障)
- 高額療養費制度(医療費の自己負担額を軽減できる)
デメリット(負担増の回避は難しい)
- 社会保険料の負担は会社にとって固定費となる
- 役員報酬を低く設定すれば負担を軽減できるが、将来の年金額も減る
- 非常勤役員として社会保険の適用を回避する方法もあるが、一定の要件を満たす必要がある
法人である以上、社会保険料は避けられないコストと考え、資金計画をしっかり立てることが重要です。
法人化による経理・事務負担の増加
法人化すると、会社が事業主体となるため、経理・税務の業務が個人事業主のときよりも煩雑になります。法人化により増える主な事務負担について整理します。
1. 帳簿作成と決算業務の負担
個人事業主でも青色申告の場合は複式簿記が求められますが、法人になるとさらに次のような業務が追加されます。
- 決算書類(貸借対照表・損益計算書等)の作成が義務化される
- 株主総会の承認を経て決算を確定し、法人税の確定申告を実施
- 減価償却の計算や棚卸資産の評価など、経理処理の専門性が増す
これにより、日々の会計処理の負担が増え、会計ソフトの導入や税理士への相談が不可欠になるケースが多くなります。
2. 法人特有の税務申告
法人は、個人事業とは異なり、次のような税務申告が必要になります。
- 法人税・法人住民税・法人事業税の申告納付が毎期発生
- 赤字であっても法人住民税の均等割(一般的な中小法人で年間7万円)が発生
- 消費税申告が事業年度単位になる(個人事業では通常1月~12月の区切り)
個人事業と異なり、法人の場合は「利益がゼロでも税負担が発生する」という点を考慮する必要があります。
3. 給与計算と源泉徴収事務
法人として役員報酬や従業員の給与を支払う場合、給与計算や税務処理が必要になります。
- 毎月の給与から所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付
- 社会保険料の計算と納付も発生
- 年末調整の実施や、法定調書・給与支払報告書の提出義務
- 住民税の特別徴収(給与からの天引き対応)
これらの業務は、専門的な知識が必要であるため、社内に担当者を置くか、税理士・社会保険労務士に委託するのが一般的です。
4. 各種届出や管理業務
法人化により、税務署や自治体へ以下のような各種届出・管理業務が必要になります。
- 法人設立届出書、青色申告の承認申請書などの提出
- 法人名義の銀行口座・クレジットカードの開設、契約名義変更
- 代表者印(実印)の管理や、株主総会の議事録作成・保管
- 株式会社の場合は決算公告の義務も発生
これらの手続きは、事業運営に直接関係はないものの、法人としての信用管理のために重要となる業務です。
5. 事務負担を軽減する方法
法人化による事務作業の増加は避けられませんが、以下の方法で負担を軽減できます。
- クラウド会計ソフトを導入し、会計業務を効率化する
- 税理士や社会保険労務士と顧問契約を結び、経理・給与計算を外注する
- 経理担当者を社内に配置し、日常業務を分担する
株式会社と合同会社の比較(設立コスト・運営負担・信用力)
法人化を決めた際、最初に考えるべきなのが「会社の種類をどうするか」です。日本で設立できる法人のうち、株式会社と合同会社が主流となっています(他に合名会社・合資会社もありますが、現在はほとんど利用されていません)。
それぞれの特徴とメリット・デメリットを比較し、どちらが事業に適しているか検討しましょう。
1. 設立コスト
- 株式会社:
- 定款認証が必要(公証人役場での認証手数料:約5万円)
- 登録免許税が最低15万円
- 設立費用の総額は約20万円以上
- 合同会社:
- 定款認証が不要
- 登録免許税は最低6万円
- 設立費用は約10万円前後
設立費用を抑えたい場合は、合同会社の方が圧倒的に低コストで済みます。
2. 運営の柔軟性と事務負担
- 株式会社:
- 株主総会の開催、取締役の任期管理が必要
- 決算公告(官報などへの公表)が義務
- 一人会社でも株主総会議事録の作成が必要
- 法的手続きが多く、運営負担が大きい
- 合同会社:
- 出資者=経営者である「社員」の合意で経営ができる
- 株主総会や決算公告の義務なし
- 役員の任期がなく、運営手続きがシンプル
ランニングコストや事務負担を抑えたいなら、合同会社の方が運営しやすいです。
3. 社会的信用・知名度
- 株式会社:
- 一般的に社会的信用度が高い
- 歴史が長く、企業間取引や融資で有利になることが多い
- 法的規制が多いため、信頼性が確保されやすい
- 合同会社:
- 2006年に導入された新しい形態のため、知名度は株式会社ほど高くない
- 小規模事業向けというイメージがあり、取引先や金融機関によっては信用力が低く見られることがある
- ただし、Apple JapanやAmazon Japanなどの大企業が合同会社を採用していることから、近年は認知度が向上している
社会的信用を重視するなら株式会社、初期の信用力をあまり気にしないなら合同会社が選択肢になります。
4. 資金調達や成長のしやすさ
- 株式会社:
- 株式発行による資金調達が可能(ベンチャーキャピタルや投資家の出資を受けやすい)
- 将来的に株式公開(IPO)を目指す場合は株式会社一択
- 合同会社:
- 株式を発行できないため、投資家やベンチャーキャピタルからの出資が難しい
- ただし、オーナー経営を続けるなら不自由はない
事業拡大を見据えた場合、資金調達のしやすさを考えると株式会社が有利です。
5. どちらを選ぶべきか?
- 初期費用や維持コストを抑えたい → 合同会社
- 法的手続きを簡単にしたい → 合同会社
- 社会的信用を重視したい → 株式会社
- 投資家からの出資を受けたい → 株式会社
合同会社でスタートし、事業の成長に応じて株式会社へ組織変更することも可能です。どちらを選んでも法人税や消費税免税などの税制優遇は同じなので、事業の将来像に合わせて判断しましょう。
6. 法人化のデメリットにも注意
法人化にはメリットが多いですが、以下のデメリットも考慮する必要があります。
- 赤字でも法人住民税の均等割(約7万円)が発生する
- 社会保険の加入義務がある(法人代表者も厚生年金・健康保険に加入)
- 一度法人化すると個人事業に戻すのは容易ではない(法人の解散手続きには費用と時間がかかります。)
法人化の判断は、「事業が継続的に成長する見込みがあるか」を考えた上で行うことが重要です。
4. 税理士による法人化手続きサポート:会社設立の手続きをスムーズに進める方法
法人化を決めたら、次に必要なのが会社設立の手続きです。会社を設立するには、法務局への登記申請をはじめ、税務署や自治体への届出、銀行口座の開設、社会保険の手続きなど、多くの準備が必要です。初めて法人化する事業者様にとって、これらの手続きは煩雑で時間がかかるものですが、ここで頼りになるのが税理士など専門家のサポートです。
税理士は税務・会計の専門家ですが、会社設立においても行政書士や司法書士と連携し、一連の手続きをサポートするケースが多くあります。税理士に依頼することで、法人設立をスムーズに進めるだけでなく、設立後の税務や会計処理も円滑に行えるメリットがあります。
この章では、会社設立の具体的な流れ、税理士が提供できるサポート内容、そして設立後の顧問契約による継続支援の重要性について解説します。
会社設立の基本的な流れ(登記・税務署への届出など)
法人設立にはいくつかの重要な手順があり、株式会社・合同会社で若干の違いはあるものの、基本的な流れは共通しています。以下のステップを押さえておきましょう。
1. 会社の基本事項の決定
法人設立の第一歩として、以下の基本事項を決定します。
- 商号(会社名)
- 本店所在地(登記する住所)
- 事業目的(定款に記載する内容。将来的な事業拡大も見据えて広めに設定)
- 資本金の額(1円から設立可能だが、信用力を考慮して適切な額を設定)
- 役員構成(取締役・出資者)
特に事業目的は、定款に記載するため、将来の事業展開を見据えて慎重に決めることが重要です。
2. 定款の作成と認証
定款は、会社の運営ルールを定めた法人の憲法ともいえるものです。
- 株式会社:公証人役場で定款認証(手数料5万円+印紙代4万円)が必要。ただし、電子定款なら印紙代が不要。
- 合同会社:定款認証は不要。印紙代4万円も不要なため、設立コストを抑えられる。
定款の作成は慎重に行い、不備がないようにしましょう。
3. 資本金の払込と設立登記申請
- 発起人(出資者)が会社の資本金を銀行口座に振り込み、払込証明書を作成。
- 法務局に登記申請を行い、必要書類を提出(定款、役員の就任承諾書、払込証明書など)。
- 登録免許税が発生(株式会社:最低15万円、合同会社:最低6万円)。
登記申請が受理されると、会社法人番号が付与され、登記簿謄本や印鑑証明書が取得可能になります。これで法人が正式に設立されます。
4. 設立後の各種届出(税務・労務関係)
法人設立後は、税務署や自治体へ以下の届出を行う必要があります。
税務関連
- 法人設立届出書(設立後2ヶ月以内)
- 青色申告の承認申請書(原則3ヶ月以内)
- 給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合、1ヶ月以内)
- 源泉所得税の納期の特例申請書(従業員が常時10人未満の場合、随時提出)
地方税関連
- 都道府県税事務所・市区町村役場に「法人設立届出書」を提出(概ね設立後1ヶ月以内)。
社会保険・労務関連
- 年金事務所:「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「被保険者資格取得届」(5日以内)
- ハローワーク:「労働保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」(従業員を雇用する場合)
また、業種によっては各種許認可申請が必要になるため、事前に確認しておきましょう。
5. 事業開始と運営準備
法人設立後は、以下の準備を整え、スムーズに事業を開始できるようにします。
- 法人名義の銀行口座開設
- 会計ソフトの導入と初期設定
- 法人用クレジットカードの作成
- 会社印(実印・銀行印・角印)の準備
- 顧問税理士の契約(記帳代行・決算サポートの体制構築)
税理士が提供できる法人化サポートの内容
税理士は「税務申告の代理」や「会計処理のサポート」だけでなく、法人化に際しても幅広い支援を提供できます。会社設立時に税理士が行う主なサポート内容は以下の通りです。
1. 会社形態や資本金額のアドバイス
法人化する際、「株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか」「資本金をいくらに設定すべきか」といった重要な判断が必要になります。税理士は以下のような観点から最適な会社形態を提案します。
- 税務面:資本金1,000万円未満に設定し、設立後2年間の消費税免税を活用するなど、節税効果を最大化する方法を検討
- 信用力:取引先や金融機関からの信用を考慮し、合同会社と株式会社のどちらが適しているか判断
- 将来の発展性:IPO(株式公開)を視野に入れている場合は株式会社、オーナー経営を重視するなら合同会社の選択が可能
2. 設立書類の作成支援
法人設立には、定款や各種届出書類の作成が必要です。税理士は以下のようなサポートを提供します。
- 定款作成のアドバイス(必要事項の検討、電子定款の活用による印紙代削減)
- 登記書類の準備サポート(司法書士と連携し、スムーズな手続きを実現)
- 税務署・自治体への届出書類の作成支援(法人設立届、青色申告申請、源泉徴収関連の書類など)
税理士は登記の代理申請はできませんが、提携する司法書士や行政書士と連携し、一括対応が可能です。
3. 各種税務相談・節税戦略の立案
法人化に伴い、税務戦略を適切に立てることで節税メリットを最大化できます。税理士は以下のような具体的なアドバイスを提供します。
- 決算月の設定(繁忙期を避け、資金繰りに配慮した決算月の選定)
- 役員報酬額の適正設定(給与所得控除の活用、法人利益とのバランス調整)
- 消費税の簡易課税制度の選択(適用基準を満たすかどうかの確認と有利な選択)
- 交際費や経費の計上ルールの説明(法人ならではの経費計上のポイントを解説)
設立初年度から適切な税務計画を立てることで、長期的に有利な経営戦略を構築できます。
4. ワンストップサービスの提供
税理士事務所によっては、司法書士・行政書士・社会保険労務士と連携し、法人設立をトータルサポートできる体制を整えています。これにより、以下の手続きを一括で依頼できます。
- 登記申請(司法書士対応)
- 税務署・自治体への各種届出(税理士対応)
- 社会保険・労務手続き(社労士対応)
- 必要に応じた許認可申請(行政書士対応)
このように、法人化に必要な各種手続きをワンストップで完了できるため、事業者様は本業の準備に集中できます。
5. 法人設立サポートを活用するメリット
税理士をはじめとする専門家に法人設立を依頼することで、以下のメリットを得られます。
- 手続きミスを防ぎ、スムーズに設立できる
- 時間を節約し、事業準備に専念できる
- 設立後の税務・会計業務も一貫してサポートを受けられる
- 顧問契約を前提に設立費用を抑えられるケースも多い
法人設立にはさまざまな手続きが必要ですが、専門家の力を借りることで、スムーズかつ確実に手続きを完了し、事業を軌道に乗せることが可能です。
設立後の顧問契約と継続サポートの重要性
会社設立はゴールではなくスタートです。設立後に事業を軌道に乗せ、適切に経営管理を行うためには、税理士による継続的なサポートが大きな支えとなります。多くの税理士事務所では、法人設立後にそのまま税務顧問契約を結び、月次の経理指導や決算・申告業務を提供しています。設立時に税理士に依頼した場合、そのまま顧問契約を継続するケースが一般的です。
1. 顧問契約を結ぶメリット
顧問税理士を持つことで、以下のメリットが得られます。
(1) 会計・税務を一括で任せられる
日々の記帳、決算書の作成、税務申告までを税理士に任せることで、経営者は本業に集中できます。経理や税務の処理には時間がかかるため、アウトソーシングすることで効率的に事業を進めることが可能です。
(2) 適切な節税対策ができる
毎月の業績を確認しながら、以下のような節税策を実施できます。
- 経費計上の最適化(経費の漏れがないかをチェック)
- 設備投資のタイミング調整(減価償却費の活用)
- 役員報酬の適正な設定(法人税・所得税のバランスを考慮)
- 消費税の簡易課税制度の選択(適用可否の検討)
経験豊富な税理士であれば、業界特有の節税ポイントも把握しており、結果として税負担を最適化できます。
(3) 資金調達や経営相談ができる
税理士は財務数値に精通しているため、以下のような支援が可能です。
- 融資申請のサポート(事業計画書の作成、金融機関との交渉)
- 補助金・助成金の活用支援(適用可能な制度の提案)
- 経営改善のアドバイス(キャッシュフロー管理、経営戦略の策定)
特に、日本政策金融公庫の新創業融資などの申請では、顧問税理士の存在が信用力につながるため、融資が通りやすくなる可能性があります。
(4) 最新の税制改正や税務調査への対応
税制は毎年変更されるため、最新の制度に適応することが重要です。
- 税制改正への対応(適用可能な減税制度や税務負担軽減策の提案)
- インボイス制度や電子帳簿保存法などの新制度対応
- 税務調査対策(事前準備のアドバイス、調査当日の立ち会い)
税理士がサポートすることで、税務リスクを最小限に抑えることができます。
2. 顧問契約の費用と考え方
税理士の顧問料は月額制となることが一般的で、法人の規模や業務内容に応じて異なりますが、相場は月1〜3万円程度です(業務の範囲による)。
顧問契約を単なるコストではなく、経営の安定と成長への投資と考えることが重要です。特に、法人経営が初めての場合、信頼できる税理士が「経営の右腕」としてサポートすることで、事業の安定と効率化につながるため、長期的に見ても大きな価値があります。
まとめ:法人化はゴールではなく新たなスタート!専門家と二人三脚でさらなる発展を
法人化は節税や信用力向上の有効な手段であり、適切なタイミングで行うことで得られるメリットは大きくなります。本記事で解説したように、売上規模や利益水準が一定ラインに達したら法人化を検討し、法人税と所得税の仕組みの違いや消費税免税の特典を活用することで、税負担を軽減し、資金繰りを改善することが可能です。一方で、法人化に伴う社会保険料負担や事務手続きの増加といったデメリットもありますが、それらは適切な専門家のサポートを受けることで、スムーズに対応できます。
特に、業界に精通した税理士をパートナーに迎えることで、会社設立の準備段階から設立後の経営管理まで一貫した支援を受けられます。税理士に相談することで、「いつ法人化すべきか」「どの会社形態が適しているか」といった戦略的な判断から、登記・届出の手続き、さらには節税対策・資金調達・経営管理まで幅広いサポートを得られます。法人化のメリットを最大限享受するためにも、信頼できる税理士と長期的なパートナーシップを築くことが重要です。
法人化は事業の成長を加速させるための手段であり、新たなステージの始まりです。適切な知識を持ち、専門家の助けを得ながら、賢く法人化を進めていきましょう。もし法人化のタイミングや手続きについて悩んでいる場合は、フルリモート対応の税理士に相談し、具体的なアドバイスを受けることで、より確実に準備を進めることができます。それが、長期的な事業の安定と成長につながる最善の選択となるはずです。